ピダハン
彼はわたしの右手に立っていて、力強くて茶色い痩せたその体は、見ているもののせいで緊張にこわばっていた。
「あそこにいるものが見えないか?」彼はじれったげに切り返してきた。「精霊だ、雲の上の存在が川べりに立ってこちらに叫んでいる。おれたちがジャングルに入ったら殺すと言っている」
「どこだ? 見えないよ」
「すぐそこだ!」一見何もない川辺を凝視しながら、コーホイは言い放った。
「川向こうのジャングルのなかか?」
「違う!あの川べりだ。見ろ!」コーホイはいらだちをあらわにする。
ピダハンとともにジャングルに入ると、彼らには見えている野生動物がわたしには見えないことがよくある。不慣れなわたしの目は、ピダハンの目のようには利かないのだ。
だが今回は様子が違った。100メートルと離れていない真っ白な砂の川辺に何者もいないことはこのわたしにだってわかる。ところがあそこに何もないのはわたしにとって間違いないのと同じくらい確かに、ピダハンたちは何かがいることを確信していた。もしかしたらあそこにはついいましがたまで何かがいて、わずかな差でわたしが見逃したのかもしれないが、みんな、自分たちが見ているもの-精霊-はなおもそこにいると言い張った。
わたしたちは目にしたのはシャーマニズムではなかった。ピダハンには、精霊に代わって、あるいは精霊に話しかけられる人物はただひとりではない。ピダハンなら誰もが精霊と話す事ができるのだ。
知識の価値はそれが真実であるかどうかでなく、有用であるかどうかにかかっている。行動するために何を知る必要があるかを知りたいと考えるのだ。行動するための知識は主として、文化的にみてどのような行動が役に立つか、という概念に拠っている。そして思想もまた、有用な行動の一部なのだ。だから文化は、その文化が発展した場所にいるとき、わたしたちにとって役に立つ道具だといえる。
だが自分にとって未知な領域にいるとき、自分たちの文化が予期していなかった精神や肉体が支配する場所にいるとき、自分の文化が障害になることもある。ある種の環境に対して自分たちの文化がほとんど備えにならなかった格好の例として、あたしは10代のピダハンの少年、カイオアーと歩いた夜を思い出す。
狭い沼のそばを通るジャングルの細い道で、わたしは大きな声でカイオアーに話しかけながら、懐中電灯の光を頼りに進んでいた。カイオアーはわたしのすぐ後ろにいて、懐中電灯など持っていない。カイオアーが突然わたしのおしゃべりを遮り、低い声で言った。「前のほうにカイマンがいるぞ、見てみろ」
わたしは道の前をライトで照らしたが、何も見えなかった。
「手に持っているその稲光みたいなやつを消せよ」カイオアーが言った。「暗くしてみるんだ」
わたしは指示に従った。今度はほんとうにまったく何も見えなかった。
わたしたちは誰しも、自分たちの育った文化が教えたやり方で世界をみる。
けれどももし、文化にひきずられてわたしたいの視野が制限されるとするなら、その視野が役に立たない環境においては、文化が世界の見方をゆがめ、わたしたちを不利な状況に追いやることなる。
わたしたちは生まれ落ちたそのときから、自分の身のまわりをだきるだけ単純化しようとする。世界は騒音にあふれ、見るものが多すぎ、刺激が強すぎて、何に注意を払い、何は無視しても大丈夫であるか決めてしまわないことには、一歩すら踏み出せないほどだからだ。知の分野では、そうした単純化の試みを「仮説」ないし「理論」と呼ぶ。科学者は自分の能力とエネルギーを、そうした単純化に注ぎ込む。
だがわたしは次第に、そうした「優美なる理論化」に満足できなくなっていた。こうした理論化に身を捧げる研究家たちは通常、自分たちが段々に真実に近しい間柄になっていくと考える。だが、自分たちをあまりに過大評価するのは禁物だ。人間は往々にして、鼻だけを見てゾウの全体像を知ることができると早とちりする愚か者でであり、たんに明るいからというだけで、落としたはずのない場所で落とし物を探そうとするうっかり者だ。
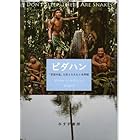 |
新品価格 |
![]()



